2024年ガソリン代の高騰に伴う報道に便乗して、ガソリンスタンドで携行缶への給油を拒否している所が増えている記事がネットニュースで流れていたのですが、ガソリンスタンドで携行缶が拒否され始めた背景には京都アニメの事件が思い出されます。
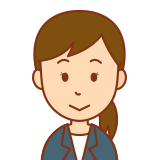
セルフのガソリンスタンドって自分で給油できるから携行缶に給油しても問題ないのでは?
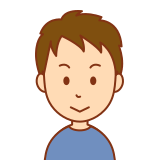
消防法では、セルフのガソリンスタンドで給油できるのは、自走する車両へのみとなっているのです。
厳密に言うと、消費者が自分で給油出来ると言う背景には、乙4種危険物取扱者もしくは甲種危険物取扱者の免状を持つ資格持ちが、安全確認して給油許可を行わないとガソリンが給油できない仕組みになっているので、自動販売機と違ってお金を入れたら、自動的にガソリンが買えるというものではないのです。
危険物取扱者の資格について
ここで少し脱線して、危険物資格者について説明しますと、俗に危険物と言われいてる取扱に注意が必要なガス、火薬、液体燃料等は、第1類〜第6類までに区分されており、危険物の資格も全6類の区分と取扱範囲の違いにより、丙種、乙種、甲種に分けられています。
セルフのガソリンスタンドで必要とされるガソリン等の液体燃料を取り扱うのは、乙種4類となります。
丙種は自分だけが取り扱える個人向けなので、事業所等で、危険物取扱者が在籍すれば、運用が可能となる乙種、ガソリンスタンドの場合だと乙種4類の所持者がいれば、セルフスタンドが営業できるという形になるのです。
ちなみに甲種は、第1類〜第6類の全てを取り扱える最上位の資格となりますが、4パターンの条件いずれかを満たさなければ、受験資格を得ることが出来ません。
セルフ式ガソリンスタンドの実情
上記のことを踏まえ、セルフのガソリンスタンドは、危険物取扱者がお客さんの給油をコントロール室で給油許可を出すことによって、給油が出来るのですが、許可を出すタイミングは、安全のために給油口に給油ノズルを入れた時になります。
たまにカウンターが0にリセットされるまで、給油口に給油ノズルを入れない方がいますが、いつまでもカウンターがリセットにならないと思ったことがあると思います。
消防法によって、お客さんが給油ノズルを持って給油ができるのは、自走できる車両の給油タンクのみとなっているので、お客自身の手で携行缶に入れることは、元々違法行為だったのです。
ただ、京都アニメの事件以降、消防署からの指導も厳しくなり、前よりもガソリンスタンドの責任も大きくなってきたのです。
人員を確保できず、派遣会社に委託している深夜帯の時間など、人件費の問題で派遣会社側のリクス回避もあり、携行缶への給油を断るガソリンスタンドが殆どになってきています。
その上、日中の時間帯でも京都アニメの事件がきっかけとなり、携行缶でのガソリン販売に関しては、免許証の番号や住所、連絡先と言った個人情報の記載が義務付けられてしまいました。
手間が増えるだけで、利益の発生しないの携行缶への給油は、ガソリンスタンドの現場には、採算の合わない負担でしか無いので、携行缶を拒否するセルフ式ガソリンスタンドが、増えているという実情なのです。
私は、携行缶でのガソリン購入拒否については、京都アニメの事件に対して、同様の犯罪を防止するために、消防庁が現場に丸投げしたやり方の結果だと認識しています。
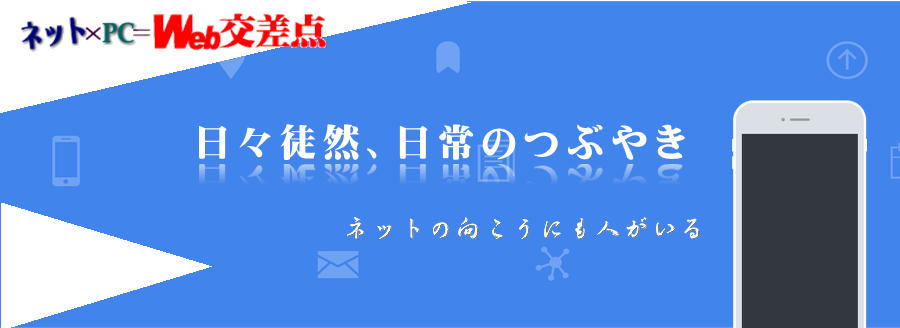



コメント