近年、AI、特に生成AIの技術進化は目覚ましく、多くの企業が業務効率化や新規事業創出のために導入を加速させていて、大企業においては、生成AIの導入率が7割を超えるケースも報告されており、AIを使う企業は増えていますけど、まだ大企業で止まっています。

もう新しい事にはついていけないよ
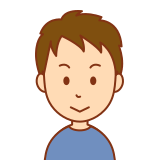
まだまだ人間が使いこなせていないので、一部の使っている人との差が開いていくのですよね。
この企業の導入熱とは裏腹に、その恩恵が一般ユーザーや全従業員の日常業務に深く「浸透」しきっているかというと、現状はまだ多くの課題が残されています。
AIが一般に浸透しきらない三つの壁
企業での導入が進む一方で、AIがまだ多くの一般ユーザーの日常や仕事に深く根付いていない主な理由は、ユーザー側の理解不足、利用メリットの不明確さ、そして提供者・組織側の課題という三つの側面に集約されます。
ユーザー側の「使い方」と「期待値」の壁
一つ目の大きな壁は、ユーザー側のスキルと理解の不足です。
日米ともに生成AIを利用しない理由として最も多く挙げられるのが「利用方法がわからない」という点です。
AIから期待通りの結果を引き出すには、適切な指示(プロンプト)を与えるスキルが必要ですが、そのプロンプトの書き方や、多種多様なAIツールをどのシーンで使い分けるべきかという知識が、一般ユーザーにはまだ不足しています。
また、AIに対して過度な期待を抱いた結果、「思い通りの回答が得られない」といった技術的な課題や、使いこなすための学習コストから「AI離れ」を引き起こすケースも見られ、期待と現実のギャップが普及を妨げています。
利用メリットと具体的な使い道の不明確さ
二つ目は、AIを導入する具体的なメリットや使い道が一般ユーザーにとって不明確であることです。
「AIが業務効率化に役立つ」と聞いても、自分の日常業務のどの部分に適用できるかが具体的にイメージできないユーザーが多いのが現状です。
明確な活用事例や、自分の仕事に直結するツールが提示されないと、「結局、何に使えばいいのかわからない」という状態に陥りがちです。
さらに、導入しても「使うメリットを感じられない」という声も多く、特に定型化された業務においては、わざわざ新しいツールを取り入れることへの抵抗感が、普及の足かせとなっています。
組織・提供者側の教育と使いやすさの課題
三つ目は、AIを提供する企業や導入する組織側の課題です。
企業内でAIツールの十分なトレーニングを受けた従業員が少ない現状があり、経営層がAIの使用に関して明確な指針やビジョンを示せていないことも、従業員の活用を妨げる要因となっています。
また、日本のユーザーは特にAIツールに「使いやすさ」を重視する傾向があります。
複雑な操作や専門知識を要するインターフェースは、一般ユーザーを遠ざけ、高性能な技術が「一部の専門家向けツール」に留まってしまう原因となっています。
AIの浸透にはまだまだ時間がかかる
あちこちから集めた情報を元に生成AIのサポートを受けて書いてみましたが、まだまだ生成AIの評価は、一般ユーザーから見て「他人事」のように扱われている状況ですね。
正直に言うとインターネットのWEBページについての価値観もAIの登場で、大幅に変わりつつあります。
企業のホームページを見ても、すぐにAIチャットが隅っこの方に出て来て、質問などを受け付けているようですが、情報不足などもあり、典型的な定型文だけを答えて、質問が意味する内容を理解出来ていないようにも感じることがありました。
まだまだ浸透するには、時間を要するでしょうが、理解度の割合が増えていけば、現在のやり方が全く通用しなくなることもあるかもしれないですね。
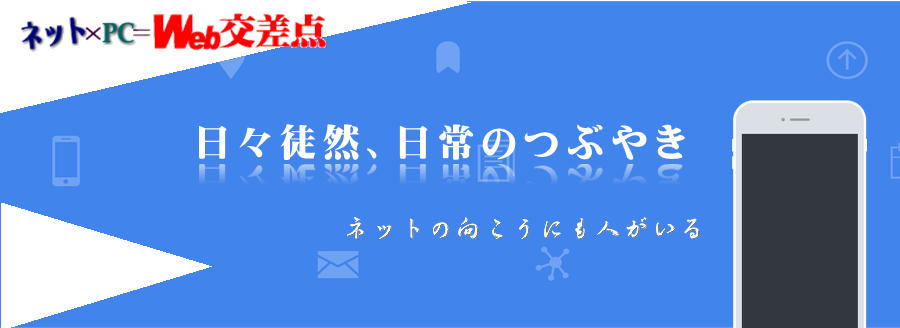
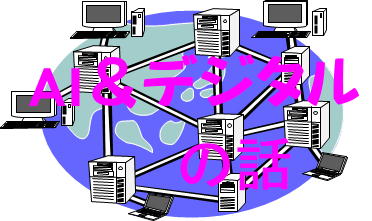

コメント